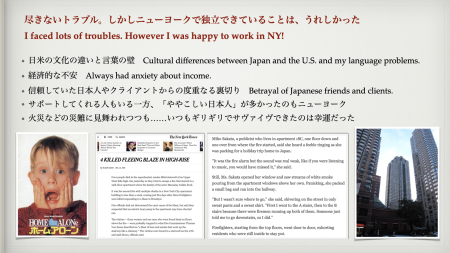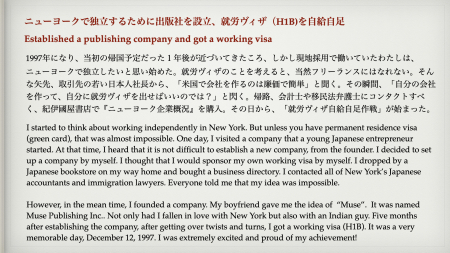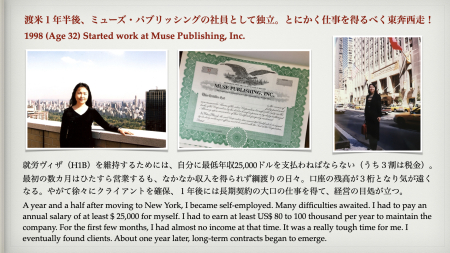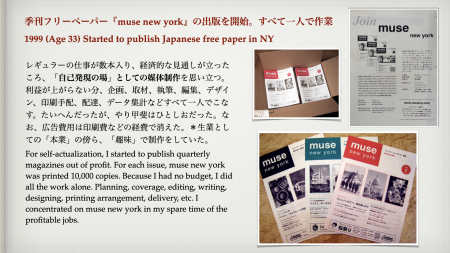インド未踏時の独身時代、2000年6月の坂田美穂。多分、人生初、デジタルカメラによるセルフィー。
🍎ニューヨークで働く私のエッセイ&ダイアリー Vol. 48
今は2001年7月9日の深夜です。ずいぶんと発行しないまま月日が流れてしまい、このままでは、インドで結婚式を挙げて戻ってくるまでタイミングを逸してしまうと、書きかけのものをひとまず仕上げました。以下、すでに時差が生じてしまいましたが、そのまま送ります。
——————————————————-
今日、7月4日はアメリカ合衆国の独立記念日です。1776年の今日、イギリスから独立したのです。一年の祝日でも最も重要度の高い今日、各地でパレードや打ち上げ花火が行われます。
今は夜の8時。あと1時間もすると、マンハッタンのイーストリバーで、恒例のメイシーズ(デパート)主催による花火大会が始まります。私はビルの屋上から眺めようと思います。
今日は祝日ながら、集中して仕事をするのにとてもいい一日でした。先週は一週間DCにいて、月曜日にニューヨークに戻ってきました。先週末は、「私的一大イベントその1」が行われましたので、その模様もご紹介します。
ところで、以前、紹介したジョージタウンのティーハウスの場所を知りたいという問い合わせがあったので、ホームページに掲載しています。写真も載せていますのでご覧ください。
さて、読者の方からこんなメールをいただきましたので、一部抜粋いたします。
——————————————————-
僕は27年前にネパールヒマラヤの山中にある、ホテル・エベレスト・ビューという所で、ラマ教で結婚式をやりました。まずホテルのある場所にたどり着くまでが大変でしたが、月がさんさんと輝いて、その明かりでヒマラヤの山々を照らし、そして星の輝きを消してしまうほどの夜空は、今思い出しても感動がよみがえります。
其の事を友人に話をすると、皆感動と驚きを持って聞いてくれ、そんな素晴らしい結婚式を実行した自分を誇らしく思っていましたが、ある時妻とけんかしたときに妻が叫んだのです。
「私だって皆と同じようにちゃんとした結婚式を挙げたかったわよ」
一瞬その場が凍りました。その時の事を長男が覚えていて、時々妻をからかっています。坂田さんは、くれぐれも同じせりふをはかないよう気をつけてください。
——————————————————-
心しておきます。
最近のメールマガジンは、結婚関連のネタが多くて恐縮ですが、あと1カ月ほどはこの話題が続くかと思います。やっぱり、仕事や他の話題より、自分の中での優先順位はさすがに高いですから、書くこともおのずと出てくるのです。というわけで、今回は、結婚式の話題です。
●結婚式アメリカ編:マリッジライセンスを取りに行く
以前も書いたが、アメリカで結婚する場合、婚姻届に名前を書いて判を押して届けて完了、というわけにはいかない。州によって法が異なるが、基本的に二人一緒にマリッジライセンス(結婚認可証)を受け取りに行き、しかるべき資格を持っている人物の立ち会いのもとに結婚式を行い、マリッジライセンスに必要事項を記入しサインしてもらった上で、改めて役所に届け出る、という過程を踏まねばならない。
ニューヨークの場合、結婚式の際、立会人が必要で、DCの場合、血液検査が必要など、何かと面倒だったので、その両方が不要だったヴァージニア州(DCに隣接)で手続きをすることにしたのだ。
先週の水曜日、会社を早退したA男と共に、ヴァージニア州アーリントンの役所(コートハウス)に、マリッジライセンスを受け取りに行く。二人の名前や住所などを記入した用紙と引き替えに、賞状のような体裁の結婚証明書(名前や日付の部分が空欄のもの)とマリッジライセンスの用紙を受け取る。受け取るとき、二人一緒に右手を掲げての宣誓が要求される。
インドで結婚式をするのだから、式は簡単に、役所に隣接する施設で挙げるつもりだったのが、それではやはり味気ないと言うことで、予定を変更。週末1泊2日で結婚式を挙げにいくことにする。
ちなみにインドでは、紙の上での手続きは面倒らしいので、基本的にはやらないつもりだ。当初はヒンズー教など宗教の問題があるのかと思っていたら、A男の家族いわく、日本大使館がややこしいことを言ってきたとのこと。具体的なことは後日聞くとして、もしもそれが本当だとすれば、やはり日本は閉鎖的で、アメリカという国は、開かれた国だと思わざるを得ない。
アメリカ人でない二人が、この国で難なく結婚することができ、それが法的に認められるのだから。
●結婚式アメリカ編:シェナンドーのB&Bで結婚式を挙げる
結局、以前にも紹介したDCから車で2時間ほどの場所にあるシェナンドー国立公園のそばで週末を過ごすことにした。ここにはワシントンと呼ばれる街がある。ワシントンDCに対し、ワシントンVA(ヴァージニア州)とよばれる小さな街は、初代大統領ジョージ・ワシントンゆかりの地らしく、彼がこの街をレイアウトしたという。なんでもDCより20年以上も前にワシントンという地名で誕生していたとか。
この小さな街には、数軒のアンティークショップと、数軒のB&B(ベッド&ブレックファスト:英米版民宿のようなもの。漫才コンビではない)やインなど小さな宿があるばかりで、あとは豊かな自然が広がっている。シェナンドー国立公園へ出かける人たちの拠点となる街(村)でもある。
周辺にはいくつかのワイナリーが点在していて、テイスティングを楽しめるほか、この季節はサクランボ狩りやベリー類狩りなどができる。
ワシントンVAの宿はどこもいっぱいだったので、さらに少し離れた村にあるB&Bに予約を入れた。そこのオーナーが、結婚式を挙げる資格を持っているので、滞在中に式を挙げてもらうことにした。
土曜日、快晴。午前中出発して、車を西に走らせる。景色を楽しもうと早めにハイウエイを降りて、牧草地帯を走る。オレンジ色の山ユリが咲いているかと思えば、ピンクや白の野の花が一面に広がり、風に揺れている。トウモロコシ畑、ブドウ畑、牛が草を食む小高い丘、取れたての野菜を売る農家の露店などを眺めながら走る。
ちょうど昼頃、B&Bに到着。2匹の犬が尻尾を振って出迎えてくれる。オーナーはイギリス出身の老夫婦。200年以上前に建てられた家屋を改装して作られた宿は、すべて英国風のアンティーク仕立て。5つある部屋それぞれが、異なる家具、調度品で調えられている。
私たちはスタンダードの部屋を予約していたのだが、夫妻の計らいで宿一番のスイートルームに通してくれた。
天蓋付きのレースがかかったベッドには、フワフワのクッションがいっぱい。飾られている調度品はヴィクトリア調。しかし、あまりにアンティークすぎて、ちょっと怖い。なにしろ、リビングの一画に、シマウマの頭の剥製が突き出ていたり、鳥の剥製が棚の上に飾られたりしているのだ。鳥はまだしも、シマウマはやたら大きくて威圧的。
A男は気味悪がって、「これ作り物だよ」と言い張るが、絶対に本物の剥製である。極力、視界に入れないよう努力した。
「どこで式を挙げたいか、決めてちょうだいね」と奥さんに言われ、私はすかさず「ガーデンで」と答えた。野の花が咲き、小さな水辺のある、芝生の庭だ。蒸し暑いけれど短時間のことだから、室内よりも外の方がいい。
私はこの間買ったばかりの裾がヒラヒラのドレスを着、A男はジャケットを着て、庭に出る。庭のベンチでご主人を待つ間、A男がポケットから紙切れを取りだし、イギリスの詩人が書いた愛の詩を読み上げてくれた。ほろっとしているところに、先ほどまで汚れたTシャツを着ていたご主人も、スーツにネクタイ姿で登場した。
私たち二人を前に、ご主人が婚姻の祝詞のようなものを読み上げる。せっかく大切な瞬間なのに、急に小バエが大量発生して、私たちの周りを飛び交う。うううぅぅ、いまいましい。宿に馬小屋があるのが原因か。小バエも祝福してくれているのだと強引に自らを納得させつつ、最後に私たちそれぞれが誓いの言葉を告げ合う。交換するべき結婚指輪を用意していなかったので、取りあえず、婚約指輪を一度外して、もう一度A男に付けてもらう。誓いのキスをして、式は終了。わずか5分ほどのことだった。式が終わった途端、小バエは去った。
式の間、私の頭の中に、佐野元春の「天国に続く芝生の丘」という曲がずっと巡っていた。7月の晴れた日に結婚式を挙げた、彼の両親のことを歌った、とてもすてきな曲なのだ。
ちなみに、私たちが式をしたこの日は6月最後の日。はからずも私はジューンブライドとなった。
さて、私たちが式そのものよりも心待ちにしているイベントがあった。その日の夕食である。なぜワシントンVAに来たかと言えば、ここには「全米で最もすばらしい」と言われるフランス料理店があるからなのだ。
その名も「The Inn at Little Washington」。レストランを擁する宿そのものがまた、アメリカでも最高級なのである。最初、料金をよく確かめずここに予約しようとして、結局、満室だったから無理だったのだが、よくよく料金を調べてみて血の気が引いた。猛烈にお高いのである。
しかし、せっかくの「特別な日」だから、食事ぐらいは奮発しようと、ゴージャスなディナーを実現するべく予約を入れた。
レストランの予約は9時だったが、6時ごろから街を散策している私たちは、周辺の、あまりの田舎さ(何もなさ)に思い切り退屈し、近所をドライブするにも同じ様な田園風景でだんだん飽きてきて、時間を持て余していた。レストランのバーで食前酒でも飲みながらくつろぎましょう、ということで、早くも7時過ぎに「The Inn at Little Washington」に行く。
建物の前には何台もの胴の長いリムジンが横付けしている。多分ワシントンDCなどからやってきた人たちだろう。牧歌的な周囲の風景とは似つかわしくない、みな晴れやかに正装をしている。
「The Inn at Little Washington」の外観は、取り立てて華美でもなんでもない、シンプルな建築物。それが宿だとわかる看板さえない。しかし一歩、建物の中に足を踏み込むと、周囲の環境とはかけ離れた別世界。王侯貴族の邸宅に招かれたようなプライベートな雰囲気が漂っている。
エントランスでは、匂い立つように美しくアレンジされた花が迎えてくれる。壁紙、天井、家具、カーテン、ランプ、ソファー、絵画、彫刻……と、目に飛び込んでくるすべてが、本物の質感と、気品に満ちている一方で、威圧的な雰囲気がない。非常に心地よい豪華さを演出している。
「9時に予約を入れているのだけれど、食事の前にバーでくつろぎたい」と告げると、とても丁寧な応対のスタッフに案内され、サロンのようなバーに案内される。ここがまたすてきなムード。座り心地のいいソファーがうれしい。
私はドライシェリーを、A男は白ワインをオーダー。紹興酒を思わせるシェリー酒をゆっくりと飲みながら、周囲の光景にゆっくりと視線を巡らせる。カップルや家族連れなどが、リラックスしたムードでグラスを片手に談笑している一方、これから食する料理への期待で、場の空気が少しばかり高揚しているように思われる。
私たちにしても、一昨日から、「結婚式、どうなるかな」という会話は出ず、「夕食、どんな料理が出るかな」とそればかりが気になっていたのだ。
話がそれるが、メールマガジンの読者から、時々「食事の話題が多いですね」というコメントをいただく。好意的なコメントが大半なので今後も書き続けることになると思うが、改めて訴えるまでもなく、「食」とは、とても大切なことなのである。
過去の記憶を蘇らせるのに効果のある要素に、「匂い」や「音楽」に並んで「食事」が挙げられるように思う。これらを媒介にして視覚的な記憶や、思考的な記憶がひっぱりだされる。
たとえば、今から7年前、私は欧州を3カ月間、ひとりで放浪した。その時に、旅の絵日記をつける一方で、食べたものを記録する「食事日記」だけも、別のノートに記していた。
たとえば、
朝:ホテルでクロワッサンとコーヒー
昼:噴水のそばで青菜入りのサンドイッチ、ピザとジュース
夜:白ワイン、羊肉のグリル、ベリーのシロップ漬け
この3行を見るだけで、地名を確認しなくても、あ、これはイタリアのアッシジだ、青菜というのはホウレンソウみたいな野菜で、名称不明だったけれど、すごくおいしかったから、数日同じものを食べたのだった。そう、この日、噴水のそばでジュースを飲んでいたとき、名古屋でエアバスが墜落する大惨事があったことを観光客に聞いた。それからベリーのシロップ漬けがおいしくて、同じレストランに翌日も出かけた。窓際の席から見下ろした夕陽に映えるウンブリア平原は、一面黄金色に染まっていた……。と次々に記憶がひっぱりだされるのである。
A男と私の5年間の記憶も、軸となるのは食である。行ったレストラン、食べていたメニューを思い出して、そのときの会話や服装、その前後のエンターテインメントなどを思い出す。
話がそれたが、「The Inn at Little Washington」である。
バーで、ちょうど食前酒を飲み干したころ、ちょうどいい頃合いで、「早めにテーブルが空いたので、よろしければどうぞ」と、窓際の、中庭に続くガラス扉の近くの席に案内された。8時過ぎとはいえ、まだあたりは明るく、窓越しに中庭の風景が見渡せる。池には蓮の花が浮かび、鯉が泳いでいる。
メニューは、前菜、主菜2品、デザートにいくつかの選択肢がある。どれにしようかと思案していると、私とA男の間に舞い飛ぶ、またもや、こんどは大きなハエ!
ちょっとちょっと! アメリカで一番のフランス料理店でハエはないでしょう。どうやら、中庭に続く扉を開けたときに、外から舞い込んできたらしい。どんなに気取っていても、この建物を出ればあたりは牧草地帯。近所では牛が放牧されているくらいだから、ハエの一匹や二匹は当たり前なのである。
静かにウエイターを呼び、ハエをどうにかしてください、と頼むと、彼は静かに、そして真剣に、窓際へハエを追い込み、さっと手づかみで外へ出した。かなり慣れた一連の行動である。彼は小声で「ハエのことは、他のお客様には秘密にしておいてくださいね」とウインクして去っていった。さすがアメリカ。くだけた雰囲気。ヨーロッパの高級レストランだとこうはいくまい。
さて、気を取り直し、料理を注文する。私は、ロブスターのサラダ、冷製とグリル2種のフォアグラ、ラムチョップのグリルをオーダー。ワインは、カリフォルニア・ナパ産のピノ・ノワール。
まずテーブルに運ばれてきたのは、デミタスカップに入ったコンソメスープ。これがもう、何とも言えず食欲をそそる序章となる。コンソメスープを一口、飲んだところで、ウエイターが、トレーに盛った見た目にも美しい、おつまみのようなスナック類をサーブする。小さなスコーンに柔らかなコンビーフを挟んだもの、餃子のようなものなど、どことなく点心を思わせる数種類の中から、好みのものを手でつまむ。その手でつまむというカジュアルさもまた、やはりアメリカらしくて肩が凝らない雰囲気を演出している。
コンソメスープとスナックの味覚のバランスがすばらしく、すでに幸せな心地。思わず頬がゆるみ、A男も私も「おいしいね」とばかり言っている。控えめに2種類だけつまんだが、もう少し取ればよかったとささやかに後悔。
さて、次はロブスターのサラダ。蒸したロブスターの身だけを取り出し、マヨネーズ風のクリーミーなソースとキャビア、サラダを添えている。新鮮なロブスターは歯ごたえがよく、噛むほどに甘みが増す。キャビアの塩味と絶妙な相性で、マヨネーズソースがまろやかさを添えている。
次なる皿はフォアグラ。「冷たいフォアグラと温かいフォアグラの結婚」と名付けられたその料理は、その名の通り、2種類のフォアグラが甘みのあるフルーツジャムのようなソースと共に供される。
私がこのディナーで最も気に入ったのが、この温かいフォアグラだった。ほどよく脂ののったフォアグラが、香ばしくグリルされている。それは霜降りの牛肉に似て、口中で風味豊かにトロリと溶ける。もうたまらん、といった感じである。
ちなみに今、深夜の12時過ぎだが、猛烈に食欲が沸いてきた。辛い。
そしてラムチョップ。好みの焼き加減(ミディアム・レア)で供された骨付きのラムは、最早、ナイフとフォームなどを忘れ、手づかみで骨に張り付いた肉もしっかりと食べてしまいたいほど、であった。
伝統的なフレンチのように、バターソースなどを使った重い料理ではなく、あくまでも新鮮な素材の持ち味を生かし、その風味を引き立てる調理法で出される料理は、ボリュームがあっても胃にもたれることなく、ほどよい加減だった。
通常、アメリカでフルコースを食すると、途中で満腹になり、とてもデザートまで到達できないのが、この日はデザートも余すところなく楽しんだ。
ちなみに私はホワイトチョコレートのアイスクリームに、温かくほろ苦いチョコレートソースがかかったもの。A男は5種類のデザートが少量ずつ盛られたサンプル風のデザートをオーダーした。
満腹度100%でコーヒーで締めくくり、幸せな気持ちで席を立った。
そういうわけで、幸せな一日だった。
The Inn at Little Washington
➡︎https://theinnatlittlewashington.com/