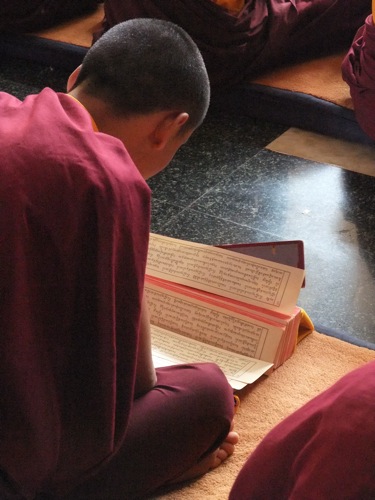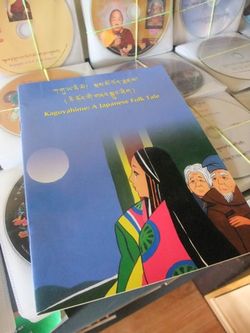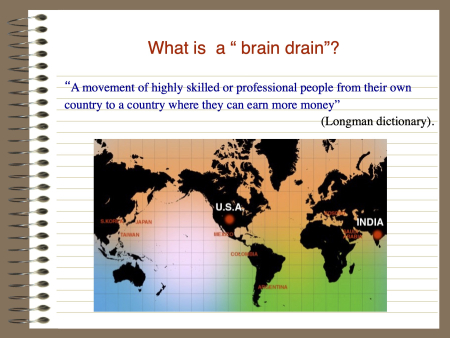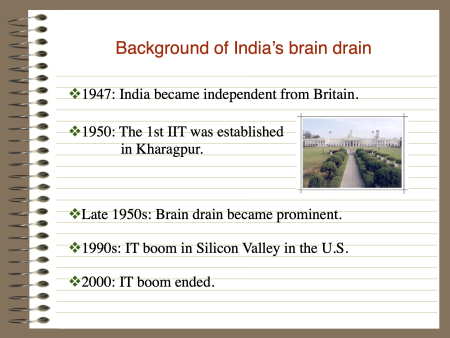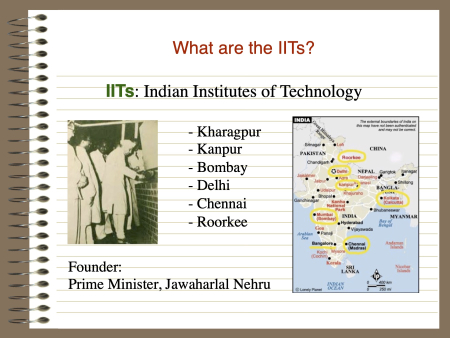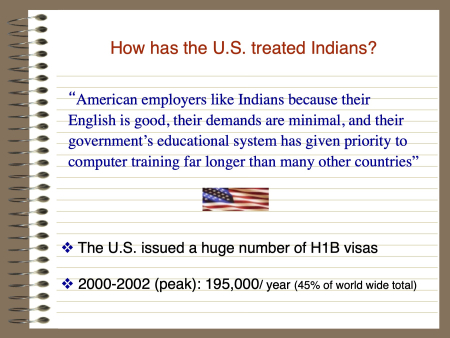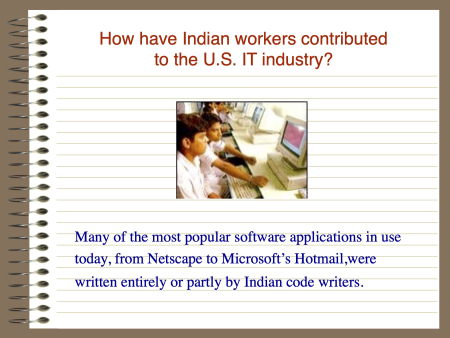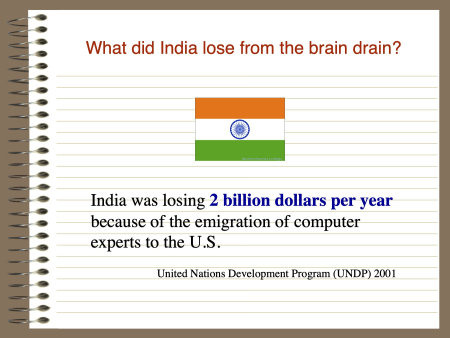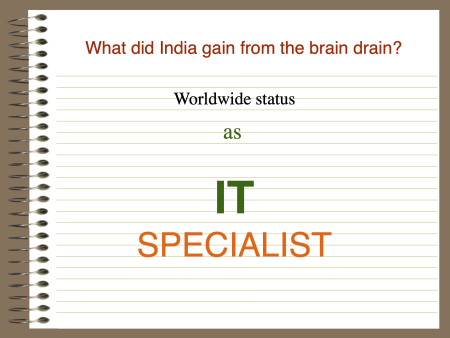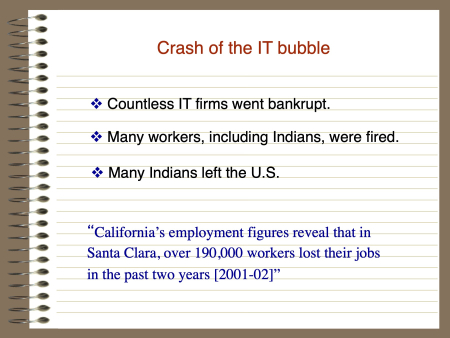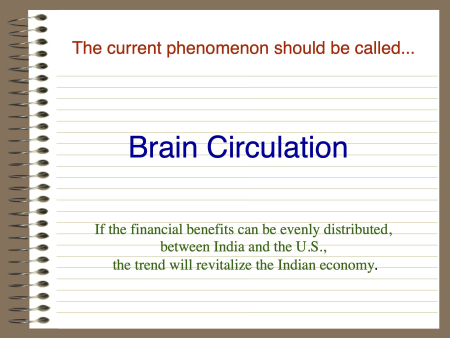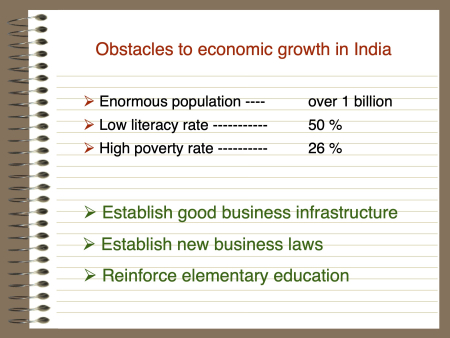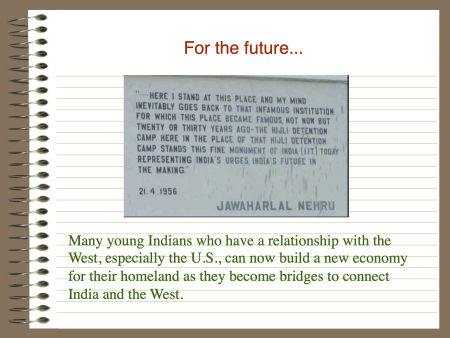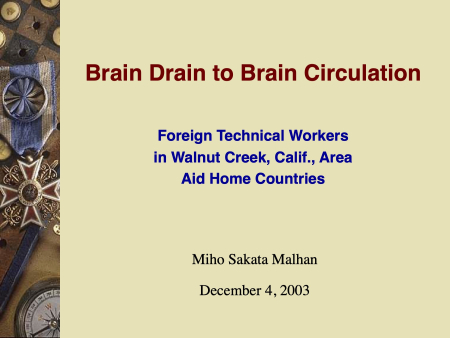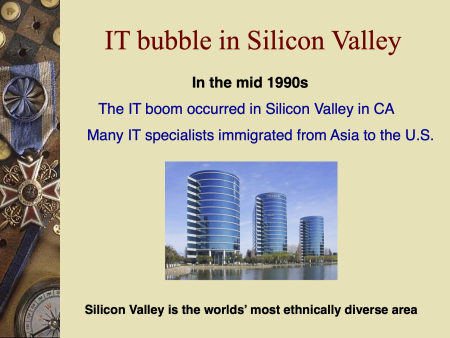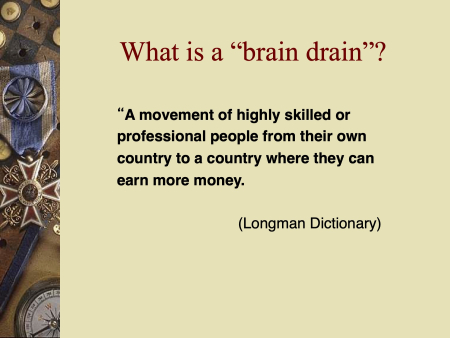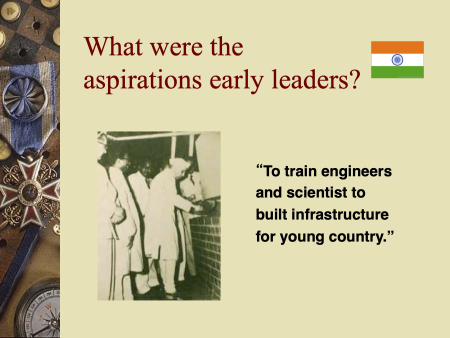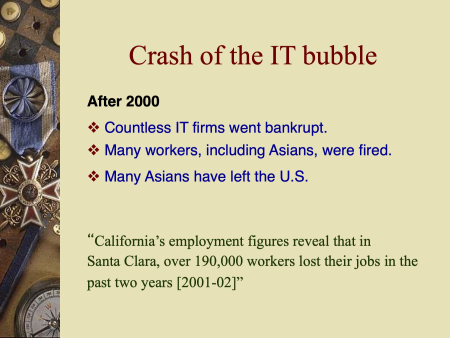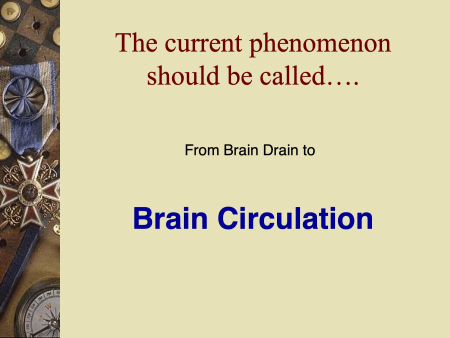今、福岡の実家に、母と二人でいます。先月の27日にこちらに来て以来、2週間あまりが過ぎました。10日間ほどこちらに滞在していた夫、アルヴィンドも、先週帰国し、わたしも17日には、米国に戻る予定でいます。
今年は身の回りで、さまざまに深く重い出来事が起こっていますが、個人的には心身共に元気で過ごしています。
書きたいをまとめる精神的にも時間的にもあまり余裕のない日々でしたが、時間の合間を縫って、買ったばかりのiBookに向かっているところです。
長々と、今回も書き連ねてしまいそうですが、どうぞおつきあいください。
——————————————————
ここしばらくの、わたしを取り巻く環境は、極めて現実的だったにもかかわらず、どこか夢を見ているような、自分の心の在処が定まらないものだった。
一時帰国していた日本から戻ってちょうど1週間後の5月22日土曜日。父はそれまで入院していた病院から、福岡市東区にある原土井病院の緩和ケア病棟、つまりホスピスに移った。
5月上旬、わたしが帰国していたときは、まだ起き上がって食事をすることも、話をすることもできた。右側の肺がすでにがんで覆い尽くされていたため、咳がひどかったものの、投薬により、それまでの数カ月に比べるとずいぶん減っていたようだ。
とはいえ、回復の見込みはないに等しかった。それまでは、何度入院しても復活するだろうと確信していたが、今回ばかりは違った。
そもそもから非常に体格がよく若々しい風体の父だったので、痩せてはいたものの、傍目には重病人には見えなかったが、事実、身体は著しく衰弱していたし、話し声も弱々しかった。
わたしが米国に戻った直後より、父の容態はどんどん悪化していき、それまでは、「まだがんばりたい」と主張していた父が、ついには、自らホスピスに行きたいと訴えたのだった。
母と妹からの報告によると、原土井病院は看護士の方々も非常に親切で、また病室などの設備も行き届いており、とても快適な環境であるとのことだった。
もう既に、何度か書いてきたことだが、父は1999年の年の瀬より体調を崩し、2000年3月に末期の肺がん(小細胞肺がん)を診断された。小細胞肺がんは進行、転移が早いことで知られ、父の場合、発見時にはすでに肺全体に転移してたこともあり、治療を受けたとしても、2年以上生存する確率はゼロとのことだった。ただ、進行が早い分、抗がん剤が効きやすい、という事実が、一縷の望みではあった。
最初の入院の後、3回再発し、3度入院した。月日を追うごとに再発の間隔が狭まり、父の体力も弱り始めていた。半年前あたりに、いつものごとく九大病院で検査を受け、またしても抗がん剤投与の必要性を告げられたとき、父は西洋医学による治療を拒否したのだった。
わたしは電話で、西洋、東洋、両方の治療を同時に勧める方法を提案したが、父には思うところがあったようで、もう抗がん剤による化学療法は受けたくないと、きっぱり拒否した。
両親は、通い始めたクリニックのドクターの言葉を信じ、高熱や激しい咳に襲われながらも数カ月の闘病期間を共に過ごした。
これまで入退院を繰り返しつつも、4年以上元気で生活をしていた父だったから、ひょっとするとこのままずっと、がんと共存しながら生きていけるのではないか、と楽観する気持ちもあった。
しかし、いずれにせよ、父の体力は限界だったのかもしれない。抗がん剤を続けていたとしても、今後、日常生活に復帰できることはなかったと思われる。やりきれない病だ。
ホスピスに移った父は、著しく衰弱していった。父のような状況、つまり末期のがん患者がホスピスに入った場合、その人の寿命を予測することは決して簡単なことではないそうだ。
苦しみながら生きながらえる人もいるし、すぐに死ぬ人もいる。
父の場合はどうなのか、誰にも予測することはできなかった。ただ、遅かれ早かれ、父の死は目前に迫っていることには間違いなかった。
●再び、日本へ。
父がホスピスに移った週末、いよいよ父の容態が悪いという知らせが届いた。今度こそは、もう、だめだと思った。わたしは週明けの月曜日、再び日本行きの航空券を手配するため、旅行代理店に電話をした。
翌日火曜日の便は、エコノミー、ビジネスクラスともに満席だった。水曜日の便は、エコノミークラスに2席空きがあった。翌木曜日はまた、全席満席だった。わたしは辛うじて空席のあったその水曜の便を、予約した。この時期、学生たちの夏休みの帰省ラッシュのため、連日のように満席が続いているとのことだった。
今回の帰国は長引くことを予測して、仕事や経理などの事務作業を前倒しに進め、家の片付けをし、不在時の夫の食事などを準備し(良妻)、一方、彼が日本に来ることも予測し、入国の際に必要なビザの申請書類を準備するなど、慌ただしい数日を過ごした。
そして出発を翌朝に控えての26日水曜日深夜、荷造りを終えてベッドに入ろうとした瞬間、電話のベルが鳴った。ホスピスで父の傍らにいた妹が、父の病室から携帯電話をかけてきたのだった。
「お父さん、もう、間に合わないかもしれないから」
妹が言った。
その日、日中は、意識があり、なんとか話ができていた父の意識が、いよいよおぼつかなくなってきたらしく、このまま昏睡状態に入ることを心配し、妹は私と父に話をさせようと電話をしてきてくれたのだった。
父は「いびきをかきながら、しかし意識は覚めていている」という、不気味な状況に陥っているとのことで、話せなくても、身体は寝ていても、周囲の物音は聞こえてはいるという。いや、聞こえているという以上に、細かい物音にも敏感に反応するなど、神経がとぎすまされているようだとのことだった。
受話器の向こうに聞こえた父の声は、「虫の息」と呼ぶにふさわしいものだった。太くてたくましく、大きかった父の声からは、もう、かけはなれた、それは恐ろしく弱々しい、別の存在だった。しかし、それは紛れもなく、死に瀕した父の声だった。
もう、父が何を言っているのかは、よくわからなかった。わたしも、自分が何を言っていいのか、わからなかった。ただ、父が何度も「ありがとう、ありがとう」と、言っていることはわかった。
「(美穂の)心は、帰ってきてくれている」とも、言っているらしかった。
「最後まで、キザなことを言うわねえ」と、傍らの母が言った。
福岡に到着するまで、30時間弱。間に合わないかもしれない。前回、帰国したときに、「もう、会えないかもしれない」と覚悟していた。病室を出る間際に手を振ったその光景が、もう最後になるだろうと心の中に刻んでいた。刻んではいたが、しかし人並み外れて生命力のある、存在感の強い父が死んでしまうことは、もしかすると、ないかもしれないとも思っていた。
電話を切ったあと、わたしは一気に数年分の涙を流した。こちらに戻って来ずに、そばにいるべきだっただろうか、と悔いているわたしに、アルヴィンドは言った。
「ぼくは、母さんの危篤の知らせを聞いて帰国したとき、母さんはすでに意識がなかったんだ。骸骨みたいにやせ細って、死にかけた母さんのそばで3日間を過ごした。ぼくは、それを経験したことを、決してよかったとは思っていない。彼女が元気なうちに、大学を休んで帰ってくればよかったと、後悔ばかりした」
彼は励ましとも慰めともつかないことを言い、美穂が自分を責める必要はなにもないと言った。
確かに、自分を責めることは無意味だし、それはわたしの性に合わないことだ。わかってはいたが、自問せずにはいられなかった。
わたしには、米国での自分たちの暮らしがある。仕事もある。帰ってこなければならなかったのだ。
世の中の、誰もが経験するはすの痛みなのに、それを経験している人は、身の回りにごまんといるはずなのに、いざ自分の身に降り掛かると、それは特殊な痛みのように思われてしまう。
翌朝、出発する前に、妹の携帯に電話をした。父は昏睡状態ながらも、まだ生きていた。「美穂姉ちゃんが帰ってくるまで、がんばってもらう」と妹は言ってくれたが、もう、急激に死へ向かっていく父を、わたしのために引き止めるのはいやだった。
それにしても、ここ数日で、こんなに容態が急変するとは、予測していなかった。どうして、この期に及んで、わずか一日、二日の違いが、こんなに決定的な違いになるのだろうか。
それでなくても長く感じる機内での14時間が、果てしなく長く感じられた。それでも、機内食を食べ、映画を見、少し寝た。父のことを考えると心が塞ぐので、思い出さないようにした。
あふれんばかりに水をたたえた感情の泉に通じる道の途中に、いくつもの柵や塀などの障害物を立てることにした。障害物を見つけたら、即座に引き返す。感情の深みに至らない。少し、鈍感にしていよう。少なくとも、ここしばらくは。そう思った。
そして27日金曜日。成田空港に到着して、福岡への便のチェックインをしたあと、妹の携帯に電話をした。午後、3時半ごろだったろうか。
「あ、美穂姉ちゃん! 今どこ?!」
妹の声は、切羽詰まっていた。福岡に到着するのは午後7時55分。病院に到着するまでには、まだあと4時間はかかる。
「間に合わないかも……」
妹は言った。
空港のラウンジで冷たい炭酸水を飲みながら、飛行機が飛び交う空を眺めていた。澄み渡った五月晴れの夕方の、穏やかな空だった。どんなに気が急いても、飛行機が早く出発することはない。わたしは、ただ、そこで待機するしかなかった。
●ホスピスへ。父との対面。
インドのニューデリーに比べると、なんてまばゆい夜景なのだろう。
そう思いながら、色とりどりの美しいネオンに彩られた福岡の町を上空から見下ろす。父は、まだ生きているだろうか。胸騒ぎも、虫の知らせも、なにも感じなかったから、まだ生きているかもしれない。
荷物を受け取り、タクシーをつかまえ、原土井病院の名を告げた。奇しくも運転手の義母が同じ病院に入院しているとかで、近道を通ってくれた。
緩和ケア病棟の入り口には、ウェブサイトであらかじめ見ていた通り、赤い支柱が立っていた。写真のキャプションに「生命力あふれる赤い柱」とあったが、ここを訪れる人に、その赤い柱は、果たしてふさわしいのだろうか、とも思った。
スーツケースをひきずりながら病室に向かう途中、看護婦さんに会った。
「坂田の家族の者ですが……父はまだ生きていますか?」
看護婦さんは答えた。
「ご親戚の方も、お集まりになっています」
父の病室の周囲には、叔父や叔母たちがいた。みな、涙ぐんでいる。広めの病室の、奥の方の、窓際のベッドで、家族や親戚らに囲まれて、鮮やかな赤いTシャツを着た父が横たわっていた。
父はすでに死んでいた。
肺がんを発症する前までは、元気が自慢の父だった。肺がんになり、抗がん剤治療を受けたあとでさえ、どこから見ても病人には見えない体格のよさと、若々しさがあった。
だから大幅に体重が減ったとはいえ、まだ70キロはあった父の身体は、病の果てに死んだとは思えない頑丈さで、顔が大きく、骨太のせいか、さほどやつれても見えず、触れれば皮膚もまだ柔らかく、しかしもう身体は抜け殻で、明らかに「物」になっていた。
「お父さん」
声をかけても、そこにはもう、父はいなかった。亡骸を見ても、不思議なくらい、悲しみがなかった。
この日、この病室には、本当に、うっとりするほど爽やかな風が吹き込んできたのだという。心地よい、その5月の風に吹かれながら、もう今朝からは意識のなかった父の傍らで、母と妹は、ひととき記念撮影をしたり、お茶を飲んだりお菓子を食べたりして過ごしたのだという。
父は、わたしが成田空港のラウンジで空を見ている頃、息を引き取ったそうだ。
母と妹は、父が最後の数日間、苦しんでいる様子を見、死に行く姿を見、どれほどか辛かっただろうかと思う。しかし、呼吸の苦しさがあったとはいえ、肺以外への転移はなく、多分、一般のがん患者に比べれば「痛み」にさいなまれることがほとんどなかったことは、幸いだったかもしれない。だから父は、とても穏やかな顔をして、永い眠りにつけた。
ところで、恥ずかしいので書くのもはばかられるが、父と母は近年、お互いを「ジョン」「マリー」と呼び合っていた。その名が何に由来するかを書くのは、更に恥ずかしいので省略するが、その愛称は、広く周囲の人々にも知られているところとなっていた。
父が息を引き取った直後、
「ジョン! ジョン! ジョ~ン!!」
と、大声で泣き叫ぶ母を見て、泣きながらも笑ってしまった妹の複雑な心境は、想像に難くない。
夜、9時を過ぎた頃、斎場の人たちが遺体を引き取りにきた。わたしたちもまた、香椎という町にある斎場に向かった。父が生きていれば、わたしはホスピスに泊まる予定でいたが、もう初日から、斎場に泊まることになった。
ホスピスを出るとき、お世話をしてくれた看護士の方々が、父の乗った車に向かい、玄関先で深くおじぎをして別れを告げてくれた。その様子に、まるで映画かドラマを見ているかのような心持ちになった。
実家のある福岡市東区周辺には、最近、新しい斎場が増えたのだという。高齢化社会で葬儀が増えることに先駆けてか、わたしたちが利用したその典礼会館と呼ばれるその斎場も、まだできたばかりだった。
前回、帰国していたとき、近くて便利だということもあり、そこで父の葬儀をしようとの話し合いを、母と妹としていた。また、宗教にはとらわれない「お別れ会」の形式をとること、つまり僧侶を招いてお経をあげてもらうこともしない、ということも決めていた。
父方は日蓮宗(南無妙法蓮華経)で、母方は真宗(南無阿弥陀仏)と、どちらもとりあえずは仏教徒ではあるが、日頃から信心深かったわけでもなく、家に仏壇があるわけでもない。
従って、葬儀の段取りなどは、主にわたしと妹と二人でやることになり、経済的にも精神的にも肉体的にも、できるだけ負担のかからない形で進めようと、話をしていたのだ。
父が生前、祖父のためにたてたお墓が佐賀県の鳥栖にある。そこに父の遺骨は納めればいい。お墓があっただけ、よかったと思う。さもなくば、インド式に、最寄りの川に流すところであった。というのは冗談だが。
宗教に囚われない葬儀をすることに関しては、近年、日本では「自由葬」とか「家族葬」というものが一般的になりつつあるということは聞いていたので、さほど世間体を気にすることもなかった。あれこれと干渉してくる親戚がいなかったことも幸いだった。
広い座敷の間に横たわった父の遺体を前にして、母が親戚の人たちを話をしている間、わたしと妹は、斎場の担当者と葬儀の打ち合わせを始めた。
とても、感傷に浸っていられるような状況ではない。
あらかじめ、妹夫婦がこの斎場を訪れ、大まかな要望と予算などを申し出てはいたから、少しは楽だったものの、やはり一からリストに沿って、決めていくのだった。
本来ならば、翌日が通夜で、翌々日が葬儀、となるところだが、翌々日が「友引」につき、最寄りの火葬場が休業だという。だからといって、葬儀を一日遅らせると、翌日が仮通夜、翌々日が通夜、そしてその翌日が葬儀、となってしまう。
母と妹は看病で疲れきっている。わたしとて、長旅のあとだから、元気いっぱいというわけではない。担当者によれば、実際、友引に葬儀をしてはならない厳密な理由はないようだ。迷信に従うよりも「ことを速やかにすませたい」というのが、わたしたちの本音だった。
聞けば、少し離れたところにある油山の火葬場は、友引でも営業しているとのことなので、そこで火葬してもらうことに決めた。
後日、NHKのテレビ番組で、最近はやり始めているという「こぢんまり葬」の特集を見た。それによると、葬儀は「三日間戦争」とも呼ばれ、この慌ただしい数日の間に、さまざまなことが瞬く間に決められていくのだと言う。まさにその通りだったと思う。
棺や骨壺の種類、祭壇の飾り付け、通夜の料理のメニュー、香典返しの品物など、カタログを見ながら一つ一つ決めていく。
「棺はどうせ燃えてしまうから安いもので(それでも5万円也)」
「骨壺は、あとに残る物だからちょっといいものを(7万円也)」
「提灯やランタンはいらない。そのかわり、生花をたっぷりと(30万円也)」
「菊は地味だから極力さけて、彩りのいい百合や蘭など、華やかな花を」
「通夜の料理は精進料理じゃないものを。アルコールはなしで」
通夜や葬儀の式次第も、その場で大まかに決めていく。僧侶を呼ばず、焼香もしないので、それに代わる「献花」の儀式を加えること、また、父の写真を映し出すスライドショーを行うことなど。
一般的な仏教形式の葬儀に比べると、はるかにさまざまを省略しているはずなのに、そろえなければならないものが実に多い。リストに連なる項目も、そしてかかる費用も、みるみる増えていく。
各項目の適正価格がわからない上、疲労困憊だから判断力も鈍る。ともあれ、葬儀に対するわたしと妹の価値観が近かったのは幸いだった。空腹だし、眠たいしで、早くすませたいこともあり、次々に即決した。それでも、数時間を要した。
そして深夜。どうにか大まかな予定が決まったのち、わたしと妹は葬儀場の向かいにあるロイヤルホストで遅い夕食を取った。
アルヴィンドには斎場に着いて間もなく、電話で訃報を知らせ、早急にビザの手配をして日本に来るよう頼んでいた。
妹と二人、疲労の極みながらも豚の角煮と中国粥のセットを食べていたら、アルヴィンドから妹の携帯電話に連絡が入った。今、日本大使館に来ているが、資料の不備でビザを発行してもらえないという。ちなみに米国人は日本に入国する際、ビザは不要だが、インド人は必要なのだ。
かような事態を予測して、あらかじめわたしは大使館に問い合わせ、必要書類を整えていたから問題はないはずだった。
レストランの外に出て、大急ぎで米国の日本大使館に電話をかけ直すと、わたしが用意していた「日本からの招待状」が、不完全だという。日本から送られた証拠となる封筒か、ファックス送信の記録が必要だというのだ。
わたしは、その「招待状」の内容を確認するため大使館に問い合わせをした際、「証拠は必要ないのか」とあらかじめ、わざわざ尋ねておいたのだが、その際、電話に出た男性スタッフが「必要ありません」ときっぱり言ったのだ。
だから、必要と言われた書類に加え、請求されていない婚姻証明書までも念のため、アルヴィンドに託していたのだった。しかし、その件を電話に出た女性スタッフに告げても受け入れられず、証拠がなければビザは出せない、の一点張りなのである。しかも、非常に無礼な口調で、それはアルヴィンドに対しても同様だった。
夫は会社を休んでビザを取りにいっている。しかも、その日を逃したら、週末をまたいでの手続きになり、いったい、何日先にこちらへ来られるかわからない。葬儀には間に合わないにしても、できるだけ早く来たいということで手続きをしているにも関わらずこれだ。
父が亡くなって数時間後で、今、斎場にいるから、今すぐに招待状などを作って送付できる状況ではない、と説明しているにもかかわらず、「それがなければビザは発行できない」と言い張り、件の職員の説明ミスについては全く言及しない。
どうしても諦めきれないわたしは、責任者に電話を代わってくれと頼んだ。10分以上も待たされた挙げ句、領事が電話口に出た。わたしは理性がはじけ飛ぶほど怒りをこめて、夫のビザを出してくれと頼んだ。こちらのミスならともかく、職員のミスが原因なのだ。しかし領事も、引き下がらない。
「わなわなと怒りにうち震える」という状況を、本当に久しぶりに経験した。
制御不能の赤ランプが点滅しているかのような感情の激しさで、大使館の不手際とこちらの正当性を訴え続けた。その結果、領事は「わかりました。ビザは本日中に発行します」と受けてくれた。いったい、何だったのだ?
通常なら「数日」かかるところが、幸か不幸か「数時間後」に発給の手続きが済んだ。アルヴィンドは翌日、旅行代理店に航空券を取りにいき、その翌日の便でこちらに来ることになった。
この件を通して、改めて、大使館や領事館の仕事ぶりのいい加減さと、一部職員の無礼さを実感した。これまでアルヴィンドが日本大使館や領事館で、どれほど「ぶしつけな態度」を取られてきたか知れない。しかし、今回だけは、本当に許し難かった。
加えて、普段は感じない、夫と自分の国籍の違いによる、得も言われぬ距離感を覚えて、疲労感が増した。悲しみと憤りが入り交じり、やりきれない心持ちで、すっかり冷えきった豚の角煮と中国粥を、黙々と平らげた。
その夜、わたしと母は斎場の広間の、父の遺体のある部屋で寝た。少しも熟睡できなかった。
●通夜の日。
28日金曜日早朝。就寝してから数時間しかたっていないのに、カラスのけたたましい鳴き声で目を覚ました。窓を開き、ヨガをして、心を鎮め、それから近所のコンビニエンスストアに朝食を買いにいく。
コンビニエンスストアの隣のメロンパン屋も開いていた。焼きたてのおいしいメロンパンも買った。前回、わたしが帰国したときに父が入院していた病院とこの斎場は、目と鼻の先にあり、だから前回もここでメロンパンを買い、父と分けて食べたのだった。
それにしても、わたしは、何につけても、泣きたくはなかった。自分でも理由はよくわからないが、泣くのはいやだった。
周囲の人々が泣いていると、ついこちらも感情がこみ上げてくるが、そんなとき、黒柳徹子の言葉を思い出した。彼女は「徹子の部屋」で人々の話を聞いていて、涙が出そうになることがたびたびあるらしいのだが、その都度泣いていたのでは、番組にならない。
涙が出そうになったときは、それを止めるいい方法がある。舌の先を軽く噛むと、涙がすっと引っ込む、と彼女が昔、コメントしていたのだ。そのことを思い出してやってみた。ずいぶんと効果的だった。
通夜は夕方から始まるとはいえ、さまざまな準備や段取りの打ち合わせなど、こまごまとした雑事があった。関係者への連絡などは、生前、父がリストアップしていたものに従い、妹と父の仕事仲間が電話をかけた。昼ごろには親戚らも集まり始めた。受付などの打ち合わせなども行われる。
午後には納棺の儀が行われた。父の身体が大きいということで、棺は特大サイズとなり1万円追加なり。経帷子(きょうかたびら:死装束)は購入したものの、着せることはせず、足下に添え、父は赤いTシャツに短パン姿のまま。
お気に入りだったヴィンテージのアロハシャツを羽織らせた。棺には、父が入院するたびに付き添っていた、「小ジョン」と名付けられた犬のぬいぐるみや、好物のサイコロキャラメル、母と二人の写真なども入れた。
斎場の1階、入り口付近にある会場で、父の通夜と葬儀が営まれる。祭壇は、こちらの希望に近い、華やかな花々で彩られたものとなった。
通夜、葬儀共に焼香はせず、「献花」の形を取ったので、弔問客には白やピンクのカーネーションを一輪ずつ、棺の傍らに添えてもらった。
弔問客の大半は十数年ぶり、いや、数十年ぶりに顔を合わせる人々で、ひたすらに、歳月の流れを噛み締めるばかりだった。無論、わたしが知っている人は限られていたのだが。
父は病気になってからの4年間というもの、それまでの仕事中心の暮らしとはうってかわり、母と過ごす時間を大切にしていた。入院していないときは、二人で一緒にあちこちに出かけた。普段の買い物も、外食も、ドライブも、いつも母と一緒だった。
母が自宅で絵を教えている生徒さんたちとも顔見知りだった。若い女性にも積極的に話しかける父は、仕事で見せる側面とは異なるやさしさがただよっていたのか、親しみを覚えてくれる人たちも多かったようだ。そういう人たちも、訪れてくれた。
会場の脇にいくつかのテーブルがあり、小さなカウンターキッチンがある。弔問客にはそこでしばらく、コーヒーを飲み、茶菓子を食べたりして、くつろいでもらった。
親戚には別室に用意された料理を食べてもらいつつ、ひとときを過ごしてもらう。こういうとき、お酒が入ると話がくどくなったり、内輪もめが生じたりする可能性がなきしもあらずとの懸念から、「ウーロン茶のみ」に徹したのは正解だった。非常にすがすがしい通夜の席であった。
弔問客は深夜まで訪れた。本来、通夜とは、一晩中起きていて、線香を絶やしてはいけない云々の慣習があるらしいが、そんなことをやっていたのでは身体が持たないので、最後の弔問客を見送った後、わたしと母は家族控え室に戻り、寝た。
妹夫婦は久しぶりに会った従兄弟たちと飲みに行った。兄弟のように過ごした幼い頃の思い出話に花が咲き、とても楽しかったようだ。
● 葬儀と火葬と。
29日土曜日。この日は朝10時から葬儀である。9時から斎場のスタッフと打ち合わせだというので早めに起き、風呂に入り、ヨガをする。斎場の一室でヨガマットを広げる人も珍しかろう。寝ぼけ眼の妹に、「こんなときこそ、ヨガはいいんだから、やりなさい」と、ポーズの伝授までもする。
葬儀は「お別れ会」との名目で執り行うことにした。通夜の折、司会の女性が、やたらくねくねと感情を込めた口調でしゃべるのが気持ち悪かったので、「できるだけ淡々と、お涙ちょうだいな雰囲気にならないよう、客観的に、爽やかに、お願いします」と頼んだにも関わらず、やっぱりくねくねしていて、辟易した。
葬儀の式次第はきわめてシンプルで、開式の挨拶に続き、キャンドルに火をともす灯火の儀、そして喪主の挨拶、友人の挨拶、電報の紹介(一部)などを経て、弔問客による献花である。
喪主である母が挨拶の際、必要であろうとわざわざ原稿を書いたのだが(といってもきわめて短いもの)、母は「わたし、何もなくても挨拶できる」と言う。少々心配ではあったが、涙ながらにも、きちんと挨拶をしていた。さすが子供時代、お遊戯会で常に主役を務めていただけのことはある。
父の旧友からのメッセージもまた、涙あり、笑いありの、非常に「聞き応え」のある内容で、それは同時に、わたしたちの知らない父の側面を教えてもくれ、あっさりとした式次第に色を添えてくれた。
父は高校時代(福岡県の嘉穂高校)から野球をしており、卒業後は日鉄二瀬というノンプロのチームに属していた。プロの選手になるには実力が足りなかった父は、母と結婚したのち、三輪のトラック一台から建設関係の仕事をはじめ、やがてわたしが幼稚園に上がったころ、建設会社を興した。
それからのち、会社は徐々に成長し、坂田家バブル時代もあった。しかし、諸事情から十数年前に会社は倒産、わたしが中学一年の時に移り住んだ、父の栄華の結晶とも思えた大きな家も、その数年前に売られていた。
それ以降は、一言では書き尽くせぬさまざまがあったが、それでも両親は、ともかくは夫婦仲良く、優雅な精神を忘れぬよう努め、生活してきたように思う。
話がそれたが、弔問客は父の仕事関係者も去ることながら、嘉穂高校の同級生や野球関係の知り合いなども多かった。
会う人会う人、わたしに向かって、
「アメリカの、お嬢さんですか? 本、読みましたよ」
と声をかけてくれる。わたしが『街の灯』を出版したとき、父は大量に購入し、友人知人らに配っていたのだ。
葬儀に来てくれた人ばかりではない。父の行きつけのレストラン、ブティック、クリーニング店にパン屋さん……、と父はあらゆるところで、本を配布(もしくは販売)していた。両親には、なぜか「行きつけの店」がやたらと多く、「顔見知りの店の人」が多いのだ。
妹までもが、父の知人に会うたびに、「アメリカの、お嬢さんですか?」と尋ねられ、常に父の近くで世話をしてきた彼女に対してはいささか申し訳ない気もしたが、遠く離れていて、これといった親孝行をしていないわたしとしては、父が少なからず「娘自慢」をする機会を作れただけよかった、あのとき、本を出せておいてよかった、と、改めて思った。
わたしは渡米以来、何度となく、父に米国を訪れて欲しいと思っていた。ニューヨークにも、雄大な国立公園がたくさんある西海岸にも、そしてベースボールの殿堂があるクーパースタウンにも。世界最古のフィールドで、いつか父とキャッチボールをしたいと願っていた。
しかし、長時間の飛行機が嫌いだとか、仕事が忙しいとか言っているうちに病気になった。しかし2001年夏、インドで結婚式をしたあと、秋にニューヨークで披露パーティーを予定していた折には、父もついに渡米するはずだった。しかし、あのテロで、パーティーも旅行も中止になったのだった。
父をアメリカに招くことができなかったことが、唯一の心残りではある。インドでの結婚式に出席してもらえたことは、思えば幸運なことだった。
葬儀のあとは、霊柩車ではなく、白いリムジンカーに乗って、火葬場に向かった。骨壺を持っている母も、父の遺影を掲げているわたしも、やはりテレビのワンシーンを模倣しているような「嘘くさい」雰囲気がしてならず、どうにも我がことだという実感がわかない。
車で1時間ほどかけて、油山というところにある火葬場へ到着した。最後の別れを告げた後、母は点火のボタンを押すのがいやだと言っていたが、幸い、それをする必要はなかった。最近ではボタンを押させない火葬場が増えているのだという。
火葬が終わるのを待つ間、待合室で、用意していたサンドイッチ(父が好きだったロイヤルホストのカツサンドなど)を広げ、専用のバスで訪れた親戚らとともに軽くランチをとる。
こんな場所で食欲が出るのだろうか、と思ったが、みな、思いのほか、食べた。
わたしは、本当に久しぶりに顔を合わせる父の姉妹ら三人とともに、語り合った。幼児期を除いては、ほとんど関わることなく暮らしてきた人々なのに、わたしと仕草や表情が似ている人たち。
父の子供時代の話、祖父母の話など、初めて聞く話に耳を傾けながら、血縁の不思議を思う。父から習ったわけでもないのに、父に似た字を書くわたしと、その父の字に似た字を書く叔母。
棺に入れられたサイコロキャラメルを見て、姉妹が異口同音に「わたしもサイコロキャラメルが好きなの」と言うあたり。子供の頃、そろって食べていたわけでもないというのに。
色とりどりの、たくさんの美しい花に埋もれた父の棺の、ふたは静かに閉じられた。
予想時間を上回り、火葬には約2時間を要した。父の骨を拾うための部屋に通される。無機質な部屋の中央の、熱気が立ち上る台の、そこに転がる、白い骨々……。それらを、もはや淡々とした表情で、覗き込む親戚ら……。
(なんて、不気味な慣習なんだろう!)
心にこみ上げたのは、図らずも、不快感だった。
わたしが人の火葬に立ち会うのは、父方の祖父が亡くなって以来、20年以上ぶりのことである。祖父のときも、骨に見入るような気持ちにはならなかったが、今回も、とても前に陣取ってはいられなかった。
悲しい、というよりは、恐ろしい、気持ち悪い、という感情。辛うじて、箸で骨をつまんで骨壺にいれたあと、後方に下がる。それにしても、なぜ、箸でつまむのだろうか、骨を。古くからの慣習には、それぞれに何らかの意味合いがあるのであろうことはわかるが、生理的に耐え難く思うのは、わたしだけではないはずだ。
骨壺に入りきれない大きな骨を、火葬場の人が、ガシ、ガシ、と砕くさまを見たときには、血の気がスーッと引いていく思いがした。
一方、葬式慣れした親戚らは、「まあ、きれいな骨」「立派な骨だこと」と、骨の品評をしている。なんて奇異な情景なのだろう。
こうして、大きかった父は、高級な白磁の菊彫り骨壺セットに納められた。いくら何でも、これに7万円は高すぎだったろうか……、いや、これは妥当な数字だったろうか……。そんなことに思いを巡らす。
その夜、母と妹夫婦の4人で、夕食に出かけた。どんなに疲労困憊でも食事は大切だ。しかし、みな、猛烈に疲れきっており、食事のあとは起きているのも辛いほどだった。
泥のように眠りたい、と思ったが、時差ぼけもあって、翌朝もまた、早朝に目が覚めた。居間の一画にもうけた祭壇で、写真の父が笑っている。
人一倍生命力にあふれていた父の、その生命が、もうどこにもないなんて、どうにも信じがたい。
通夜、葬儀を通して、わたしは、父にゆかりのある人々に会い、言葉を交わした。そして、わたしは父と過ごした時間がいかに少なかったかを痛感した。
妹が生まれるまで、つまりわたしが3歳のころまでは、父と二人で出かけた記憶がある。しかし、それ以降の父の思い出は、主に父は仕事一色だった。更にはわたしが中学2年のときに「大反抗期」を迎えて以降の数年間は、父とまともに口をきいた事がなかったから、具体的な父との交流は、きわめて少ない。
大学進学に伴い、18歳で実家を出てからも、母とは電話でしばしば話していたが、父と話すことはほとんどなかった。成人してから、父と二人で食事に出かけたことはただ一度。わたしが東京で働いていた頃、やはり仕事の都合で上京した父と、銀座の料亭で夕食をとった。
店の女将さんがわたしたちを見るなり、
「まあ、親子お揃いで、よろしいですねえ」
と、微笑みながら声をかけてきた。わたしと父は、とてもよく似ているのだ。
つまり、わたしには、父と過ごした思い出が、母や妹や、父の仕事仲間や友人らに比べると、もう、圧倒的に少ない。少ないからこそ、少し冷静な心境でいられたのかもしれない、黒柳徹子の技が使えたのかもしれない、とも思った。
●夫の来日。
そして30日日曜日の夜、アルヴィンドが福岡に到着した。一週間ほどの滞在予定にしたかったらしいのだが、航空券がとれず、6月9日までの約10日間、滞在するという。
幸い、大切な打ち合わせなどもなく、すんなりと休みを取れたことは幸いだった。葬儀には間に合わないにしても、日本語が話せないにしても、彼はわたしの夫であり、このような状況下においては、どんな国においても、夫婦が共にいることは自然な流れだろう。
わたしたちはこれまで福岡を訪れたとき、ホテルに滞在するのが常だったが、今回ばかりは実家に泊まることにした。客間や和室のない実家だから、父の書斎のフロアに布団を敷き、そこで休むことになった。
翌日からの1週間は、奇しくも妹の夫の「リフレッシュ休暇」だった。妹夫婦にしてみれば、そもそもワシントンDCに遊びにくる予定にしていたから気の毒ではあったが、一方、都合がよかったといえば、よかった。
●母とわたしと夫との生活。
朝な夕なに泣く母に、優しく手をかけて、「ダイジョウブ?」と言うか、あとは英語で話しかけるしかできない夫。
とはいえ、文化の違いなどにより、我々とはピントのずれた彼が一緒にいてくれたことは、ありがたかったとも言える。
父の遺影の前に、常に置かれる父の好物。果物やお菓子だけでなく、ご飯さえも添える母を見て、アルヴィンドがわたしに耳打ちをする。
「ねえ、美穂のお母さん、大丈夫? どうして、あんなに食べ物を飾るの?」
わたしが日本の習慣を簡単に説明すると、
「死んだ人に食べ物を供えるなんて、非科学的!」とのこと。
わたしが葬儀や火葬のようすを事細かに説明すると、やはり遺骨を拾って箸で骨壺に詰めるという儀式に驚いていた。
ちなみにインドでは、遺体は火葬され川に流される。彼の母は、一般の火葬場ではなく、彼女が経営していた農場に櫓を組み、そこで火葬し、ヤムナ川に流したそうだ。遺体への点火は長男の仕事であるらしく、アルヴィンドが行ったとのこと。あまりにも辛い経験だったらしく、細かい事は聞けなかった。
●それなりに、楽しい日々。
父の死後まもないからといって、葬儀が終わった後は、これといった行事はない。「宗教にとらわれない」葬儀をしたため、初七日などもしない。
無論、さまざまな名義変更など、各種手続きなどの事務処理はあるが、それは随時、片付けられることで、面倒だが仕事だと思えばたいしたことではない。
家にいる間、アルヴィンドはコンピュータに向かい仕事をしているか、バイリンガルのテレビ番組を見るか、読書をしていた。時折やってくる訪問客には、部外者としてではなく家族の一員として挨拶をし、その様子がとても奇妙なものに思えた。
夫には、それまでわたしの家族の詳細を、しみじみと語ることはなかった。この期に及んでも、わたしは当初、夫に詳細を語るのをためらっていた。建設業を営んでいた父は、ちょっぴり「やくざ」な側面もあり、夫に話しても理解されないであろうことも少なくなかった。
しかし今回は、価値観や文化の違いによる誤解が生じることをも承知の上で、家族のことをできるだけ、話した。夫は、今までにない神妙さで聞き入ってくれた。彼から、的外れとも思える超客観的な意見を聞くことで、気持ちがほぐれることもあった。
ある夜、身近な親戚に集まってもらい、お礼を兼ねての会食を催した。普段なら、わたしが通訳をしないと不機嫌になるアルヴィンドだが、日本語の嵐に巻き込まれつつ、彼は黙々と箸を口に運び(おいしい中国料理だったのは幸いだった)、ニコニコとしていた。
「ぼくも、あいさつをしたい」と、自ら進んで親戚らの前で、父に対する哀悼の言葉などをスピーチしてくれたことも(もちろん、わたしが通訳したのだが)、ありがたかった。
数日は外出する気にはなれないという母をおいて、わたしとアルヴィンドは妹夫婦と夕食に出かけたりした。それどころか、数日後には1泊2日で黒川温泉にまで、ドライブに出かけた。
母も連れて行きたかったが、無理に誘うのもよくない。かといって我々も、四六時中、家にいたのでは気が滅入ってしまう。というわけで、慰安旅行を敢行したのである。
ろくに下調べもせず見つけた宿(ふもと旅館)だったが、温泉の種類も多く、わたしもアルヴィンドも大いに楽しんだ。浴衣姿で、ひなびた、しかし風情のある温泉街をそぞろ歩きつつ、他の宿の湯巡りも体験した。
品数の多い料理に舌鼓を打ち、ビールや日本酒を飲み、そしてしばしののち、また湯に入り、眠る。黒川温泉には何度か訪れたことのある妹夫婦も、今回はいつも以上にリラックスして、楽しめたようだ。
父が亡くなってしまった悲しみがあると同時に、ひとつの大きな心配ごとが消え去ってしまったことへの安心感も、そこにはあるのかもしれない。
翌日は、父が好きだったという久住高原をドライブした。見晴らしのいい緑の山道をすり抜け、フラワーガーデンにも行った。抜けるような青空と、鮮やかな緑の山並みを背景に、オレンジや黄色のポピーが、ふんわりと一面に咲き乱れるさまは、格別の美しさだった。
ガーデンを散策するのが好きなわたしたちは、心地よい風に吹かれながら、花を眺め歩いた。オムレツカレーを食べ、フライドチキンを食べ、ジャージー乳のソフトクリームを食べた。
妹夫婦と両親は、4人でこのあたりにもドライブに来たことがあるらしく、妹にとっては、どこを見ても父を思い出されてやりきれなかった様子である。
この周辺ばかりでは、もちろん、ない。福岡県下および周辺地域全域において、父の足跡は至る所に残されており、どこを見ても、何を見ても、母にせよ、妹にせよ、父を思い出さずにはいられない様子である。
特に食べることが大好きで、グルメ情報も豊富に蓄えていた父は、あちこちのレストラン情報にも精通していて、周囲に伝授するのが常だったようだ。そんな父にゆかりのある店が、道中に幾度も現れ、そのたびに、妹は父をしのぶ。
アルヴィンドとは、時間の合間を縫って、天神や博多などへ出かけたほか、近所のショッピングモールに出かけてマッサージをしてもらったり、また、最近できたばかりのダイヤモンドシティという巨大なショッピングモールを巡った。アルヴィンドは食料品売り場での「試食」を満喫していた。
また、海の中道にある水族館へ行き、イルカのショーを見たりもした。大規模な水族館で、わたしたちは数時間を過ごした。
最後の日には、わたしが幼少期を過ごしたあたりを、二人で散歩した。
わたしが通っていた名島幼稚園の前を通り、2歳か3歳のころ、祖父と散歩した山道を通過し、1歳から13歳までの歳月を過ごした小さな家の前を通った。何もかもが、信じられないほど小さく見えた。通りも狭く、1ブロックがとても短い。
多くの家が改築されていて、しかし見覚えのある表札の名前を目で追いながら、幼い頃、よく遊んでいた、遠い日の友達の顔を思い出す。
町内唯一のパン屋だったニコニコ堂はなくなり、汐見マーケットは廃れ、食料品の浜松やさんも、鮮魚の荒巻さんも、店を閉じていた。
その分、新しい店や建物も、できていた。かつて、父の坂田建設株式会社だった小さなビルを横目で見がなら、こうして、アルヴィンドと二人で、自分の子供時代を過ごしたあたりを静かに歩くことの不思議さに、わたしは静かに、打たれた。
父が行きつけだったという、わたしにとっては新しいパン屋さんに立ち寄り、父の好物だったという天然酵母の食パンを買った。アルヴィンドは好物のエクレアを、わたしはシュークリームを買った。
● 父の名残。
母の影響もあり、おしゃれな父だったので、衣類や小物は捨てるには惜しい物がたくさん残っていた。まだ新しい革ジャンやコート、セータやジャケットなどもあるが、小太りのアルヴィンドをはじめ、妹の夫や従兄弟たちにも大きすぎて着られない。
それでも、妹の夫や従兄弟たちは、父のキャップやベルト、ネクタイなどを喜んでもらっていった。アルヴィンドは、父のものを身につけるのは気が進まないだろうと思ったが、真新しいベルトやカフス、ネクタイをもらった。
わたしは、父の書斎を整理しながら見つけた、父が好きなマーカーぺン(豪華10色入り)や、父が掃除の際、愛用していたというドイツ製のスポンジ「激落ちくん」(洗剤なしで本当によく落ちる)の買い置きなどをもらう。その他こまごまとした文房具類など。
それから、まともなところでは、真珠貝でできたタイピンも。これは自分のブローチか指輪に作り直そうと思う。そうやって、父の部屋を幾日かに亘って片付けては見るものの、なかなか先に進まない。
几帳面な文字で綴られた食事の記録や、体温や血圧などが記されたここ数年のノートに読み入ったり、仕事の書類をめくったり、埃をかぶった古いアルバムを開いたり……。
ユニフォームの背番号、いくつもの野球ボール、同窓会の文集……。父の青春時代の名残が、次々に出てくる。ついでに自分たちの子供時代の写真に見入ったりして、作業は悉く中断する。
一方、母は、寝室や、キッチンや、家の随所を片付けるにつけ、父のひとつひとつを思い出し、そのたびに泣く。
父の衣服。父の薬の残り。父のおやつ入れの引き出し。父の好きな食品の買い置き。父の好きな紅茶。父の好きな寿司屋。父の好きな天ぷら屋。父の好きなパン屋。父の乗っていた車。父の買い集めた旅行雑誌……。
あたりに満ちあふれた父の気配を、これからさき、時間をかけながら、少しずつ、少しずつ、薄めながら、でも決して消えてしまうことのない父の面影を、涙を流すことなく思い返せるまで、いったいどれほどの時間がかかるのか、わからない。
心が迫る季節には、母にアメリカへ遊びにきてほしいと思っている。何年後かに、わたしたちがインドに移住できたなら、インドにも遊びにくればいいと思う。あるかどうかは知らないが、熟年対象のパーティーなんかに参加して、ボーイフレンドを作るのもいいと思う。
40年以上の歳月を、共に過ごした人を失うことがどういうことなのか、想像することさえ、気が重い。が、いつまでも沈み込んだままではいてほしくない。
今はただ、季節が一巡し、二巡し、父のいない、母の新しい思い出が増えていくことを、ひたすらに待つばかりだ。
(6/14/2004, Copyright: Miho Sakata Malhan)